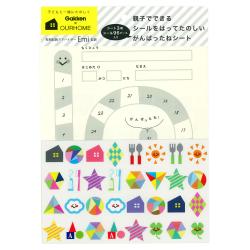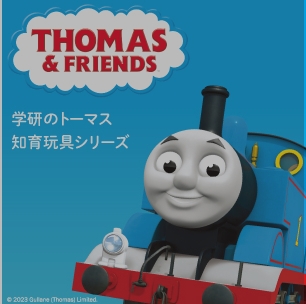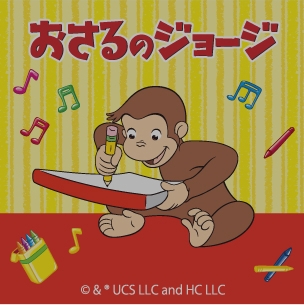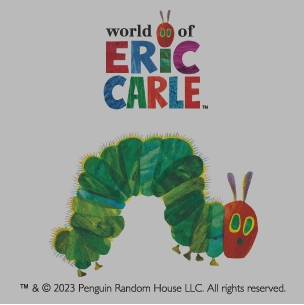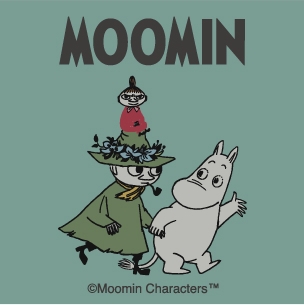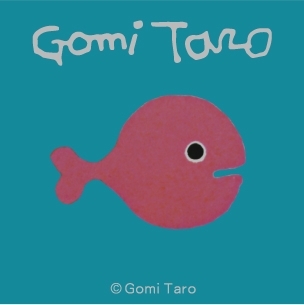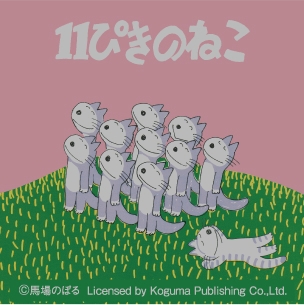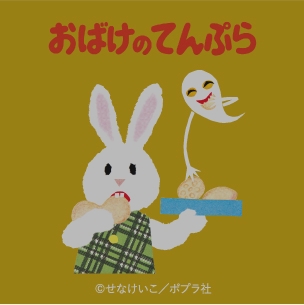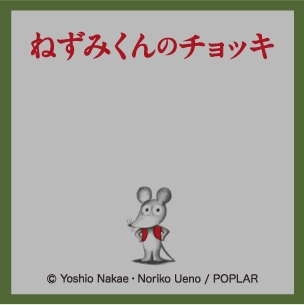入園や入学、進級を経て始まった新しい環境に慣れてきたタイミングで、「園や学校で困らないように、生活習慣を身につけたい……」と考えるママやパパもいるのではないでしょうか。
そんなお悩みに対して、「親がゴールを決めて焦る必要はない」と語るのは、教育評論家の親野智可等先生。子どもが、無理なく楽しく、身の回りのことを自分でできるようになるための工夫を教えてもらいました。
新生活に向けて身につけておきたい生活習慣は?
「毎年この時期になると、『出かける準備や朝の身支度、整理整頓、お手伝いなど、入園・入学前にどこまでできるようにしておくべきですか?』という質問が私のもとにもたくさん届きます。文字の読み書きや数字など、勉強に関することも同様です。
でも、その前に考えてもらいたいのは、『〇〇ができるように!』と先にゴールを決めずに、目の前の子どもをよく見るということ。まずは、お子さんの得意や不得意を知ることが大切です」(親野先生)
親として「あれもこれも」と焦ってしまいがちですが、じつは、その子自身に目を向けることが、生活習慣を身につけるスタートラインになる、と親野先生はいいます。
「入園前から自分で朝の準備ができる子もいれば、卒園時期になっても準備がうまくできない子もいます。1人ひとりの成長に個人差があるように、その子にとっての『苦手』も違うわけです。

苦手なことは、生まれながらの特性も影響するため、その子が悪いわけでも、親のしつけや指導が悪いわけでもないんですね。そのため、親としてできることは、シンプルに“声かけ”と“方法”のふたつの工夫しかありません。
声かけに関しては、できないことを指摘して、何度も注意をしたり、叱ったりするのではなく、伝え方を変えましょう。マイナスの言葉を使わず、ポジティブな言葉に言い換えることが重要です。
そして、もうひとつ大事なのは、方法の工夫です。何度も注意して親子ともにストレスを抱えるよりも、『どうしたら苦手なことに取り組みやすいか』、『子ども自身が気づいて行動しやすいか』ということを考えるほうがずっと効果があるのです」(親野先生)
シーン別!子どもの「やってみたい」を育む関わり方のコツ
では、具体的にどのような工夫ができるのでしょうか。シーン別におすすめの方法を教えてもらいました。
朝の準備は「時間の見える化」で解決
朝ごはんや歯磨き、着替え、荷物の確認……朝の準備はやることが盛りだくさん。出かける時間に間に合うようにすべてを進めるのは大変です。
「時間は目に見えないからこそ、あとどれくらいで準備を完了させなくてはいけないか、子どもが実感することはとても難しいもの。『早くしなさい』と言うより、時間を“見える化”しましょう。

アナログの時計を用意して、その隣に『朝食を食べ終わる時刻』を指した時計のイラストを並べておきます。
長い針の位置を比べながら、『ここまでに食べ終わろうね』と伝えれば、残り時間が目に見えて減っていくので、子どもは針の動きを見ながら、食べるスピードを調整できるようになるんです。
この方法なら、親に急かされてイヤイヤ動くよりも、自分自身で時間を意識して行動するという習慣が身につきやすいと思いませんか?
朝だけでなく、お風呂に入る時刻、布団に入る時刻など、いろいろなことに応用できる方法です」(親野先生)
タスクを一覧表にしたり、イラストにしたりして見える化するのもおすすめだそうです。
「ミッションをクリアできたら、好きなイラストのマグネットを貼るなどの工夫をすると達成感を得られます。
ひとつ達成するごとに“リトルサクセス(小さな成功体験)”が感じられると、子どものモチベーションアップにつながります」(親野先生)
関連特集:はじめての“とけい”
「共感と楽しい提案」で整理整頓やお片付けもクリア
部屋の片付けや荷物整理、玄関の靴をそろえるといったことも、なかなか身につけるのが難しい生活習慣かもしれません。

「できていない点ばかりに目がいきがちですが、できるだけ子どもをとがめる言葉は使わないように心がけましょう。
『片付けないとダメでしょ!』といった否定的な言葉はぐっとこらえて、『使ったら元の場所に戻しておくと、お部屋が綺麗になって気持ちいいね』と言い換えるのがポイントです。
また子どもの気持ちに共感することも大切にできるといいですね。『今日は疲れちゃったから、靴をそろえるのも面倒だよね~』と声をかけたあとに、『でも玄関が靴でいっぱいになっているから、靴箱にしまおうか』と提案してみるのもおすすめです」(親野先生)
お手伝いは「子どもの興味関心がある」ものを
お料理やお風呂洗い、花の水やりなどのお手伝いも、親として積極的にやらせたいことのひとつ。お手伝いを通して、さまざまなことを学んでほしいと願う保護者も少なくありません。
「大切なのは、子どもの興味があることを優先して、それに関するお手伝いを促すことです。
たとえば、料理は集中力や物事の見通し、数の量など数学的思考など、教育的要素が高いのでチャレンジさせたいお手伝いのひとつかもしれません。ですが、料理にまったく興味がない子に対して無理やり勧めても、親子ともにしんどくなってしまうんですね。

日常生活の中で、子どもをよく観察していると、きっと何かしら『やってみたい!』と好奇心が芽生える瞬間があると思います。そのチャンスを逃さずに、手伝ってもらってみてはいかがでしょうか」(親野先生)
親が手を貸すのも自立のサポートに。子どもの気持ちに寄り添おう
子どもが楽しく取り組めるように工夫するのはもちろん大切ですが、それでも、なかなかできないときは、積極的に手伝ってあげてほしい、と親野先生は語ります。
「じつは『子どもに対してやってあげてばかりいると、いつまでたっても1人でできるようにならない』というのはまったく逆で、手を貸してあげたほうが子どもは自立するということが、児童心理学の研究でわかっています。
特に新生活が始まった4月5月は、お子さんは園や学校でがんばっています。だからこそ、おうちでは甘えたくなることだってあるのではないでしょうか。
それに、子ども自身が困ったときに、『手伝って』と言えることも、社会に出ていく上で大切なスキルです。ですから、『こんなこともできないの?』などと叱らずに、親子の触れ合いのひとつだと思って楽しく手伝ってあげてください。
心が満たされると、大好きなママパパに『見てもらい』『ほめられたい』という思いが生まれて、自分1人でできるようにがんばることだってあるんですよ。
その子なりのスピードで少しずつ、確実に成長していますから、その視点を忘れずサポートしてほしいと思います。子ども自身の興味関心とやる気を大切にしてくださいね」(親野先生)